
「よりよい未来をつくるために、私たちには今、何ができるだろう」
予測困難かつ複雑で一筋縄では解決できない問題があふれている現代。刻一刻と状況が変わりゆくなかで、常に自分たちや世界に問いを投げかけ、社会のために悩み、考え続けようとするチームがあります。
「株式会社インクワイア(以下、インクワイア)」は「問う、探究する」をテーマに活動する編集デザインファームです。メディア運営や、クライアント企業への編集、デザインリサーチを元にしたコンサルティングなど、編集とデザインを軸に数々のプロジェクトを手がけています。今回募集するのは、長野県内を主なフィールドにプロジェクトの実装をアシストするインターンスタッフ。一緒に悩み、考え、走りながらよりよい社会を模索していく仲間を募集します。
インクワイアと実現していく社会とは一体どんなもので、どんな可能性を秘めているのか。インクワイアの創業者で代表取締役のモリジュンヤ(もり・じゅんや)さん、取締役の山本円郁(やまもと・えんゆう)さんにお話を聞きました。
※インタビューの写真は、中山道で塩尻側の玄関口となる鳥居峠で一部撮影されました
「決めない」と決めた、就職活動
インクワイアという社名は、英語の「inquire=問う、探究する」から来ています。モリさんがこの言葉と自身の活動の重なりを見出したのは、個人事業主時代でした。
モリさん「個人でやっていた時も、編集やライティングの仕事をバックボーンとしながら、必要とあればワークショップのファシリテーションや映像やイベントの企画などを行なうこともありました。伝え方の手段が変わり、活動が広範囲に及んでいくなかでも、常に一貫してやってきたのは、『こういうテーマが大事なんじゃないか』など、問いを立てたり、投げかけたりすること。インクワイアという名前はそこから生まれました。言葉が定まった時がちょうど組織化するタイミングと重なって、そのまま社名になりました」

どんなジャンルに対しても興味を持って取り組むことから、自分自身を「雑食」と語るモリさん。そうなる直接的なきっかけとなったのは、学生の頃の就職活動でした(モリさんの今につながる大学時代〜社会人経験などキャリアに迫ったvisionsの記事はこちらから)。
モリさん「就活のタイミングでリーマンショックが起きて、検討していた企業が潰れてしまったり、採用を取りやめる企業が出てきたり。就職したからといって安定するわけじゃないということを目の当たりにして、『もっと能動的に自分の人生に主導権を持って生きていった方がいいのではないか』と思うようになりました」
そこからは、将来的な独立や起業も見据えながら就職先を考えるようになったというモリさん。しかし、面白いと思った会社の事業やテーマを本などで調べたり学んだりしていくうちに、今度はどんどん決断することが難しくなっていったといいます。
モリさん「知れば知るほど決められなくなったのですが、それは自分の知識や経験、決める上での判断材料が全然蓄積できていないからだなと。そこで一旦就活自体は保留としながら、大学以外のところに積極的に出向くようになりました。その時に出会った“変わった大人たち”とのつながりが、今の自分の考え方やあり方の土台になっているのかも知れません(※)」

「決めない」ことを決めたモリさんが、最終的にたどり着いたのが「メディア」だったのは、自分が関心の持ったテーマに関して継続して探究できる環境があると考えたから。以来、メディアコミュニケーションを起点に、ソーシャルやテクノロジー、スタートアップ、まちづくりなど、さまざまな分野を横断しながらモリさんは探究を続けています。
※この頃に出入りしていた場所のうちの一つ「IID世田谷ものづくり学校」は2025年4月から「HOME/WORK VILLAGE」という名称でリニューアルオープン。インクワイアの東京事務所もこの中にある
探究することは生きる上でのウェルビーイングにつながる
「一人ひとりが探究したいテーマをもち、その活動を継続できていることは、人のウェルビーイングにおいて非常に重要」と語るモリさん。しかし、周囲を見回すと「自分はまだ探究したいと思うテーマと出会えていない」と感じていたり、「そもそも自分にはそんなテーマはないのではないか」と思い込んでいたりする人も多いといいます。

モリさん「今は、何か一つができるようになれば将来安泰、という時代ではなく、常に何らかのテーマを自分なりに設定して、成長し続けることが求められています。ただ、外部からのプレッシャーで動くばかりだと結構つらいですよね。まずは内発的な動機にもとづいた探究による自己の変容があり、それが結果として成長につながる。こうしたサイクルをどう持続的に起こし続けることができるのかが、僕らのなかでの大きなテーマの一つかなと思っています。経済的、社会的な側面だけでなく、自分が純粋に面白いと思うものや、どんどん知りたくなるものがあった方が人生は楽しく、プレイフルですよね」
インクワイア内でも、内なる探究心を土台とした事業化や事業運営を意識して行なってきました。デザインの可能性を探究するメディア「designing(デザイニング)」の事業譲受にいたる一連の動きにも、そうした姿勢を見ることができます。

モリさん「特に、メディアに関しては自分が探究したいテーマがあってそれを周囲に共有していくこと自体が活動の持続性にもつながるし、コンテンツのユニークさにもつながります。儲かるからやるのではなく、探究したいからやるからこその競争優位性が生まれるんです。小山さんとは、彼がdesigningを立ち上げる前からインクワイアで一緒に働いており、『探究テーマは何か』、たびたび問いかけていました。最終的にはマイメディアのような形でスタートしましたが、長い目で継続させることを考えると、事業として成立させることも重要です。そこでインクワイアが持っているリソースなども共有しながらであれば、ある程度事業としても軌道にのせることができ、そこに使う時間をもっと増やすことができるのではないかという話になり、インクワイアが事業を譲受することになりました。今も事業をリードしているのは小山さんで、独自性やオーナーシップを保ちながら運営することができています」
常に経済性や成長を求められる資本主義社会のなかでも、個人の好奇心や探究心から萌芽したプロジェクトのアイデンティティを損なわず、きちんと収益を確保し、育てていく。そうしたモリさんやインクワイアのスタンスに共感した人のひとりが、2022年からインクワイアの取締役となっている山本さんです。

おふたりの出会いは、お互いに東京のベンチャー界隈で仕事をしていた10年以上前に遡ります。以来、たびたび顔を合わせては近況報告をしあうような関係でした。
山本さん「長野県に移住してから、自分なりに文化や自然との関わり方について探究をしていたのですが、東京などの都市部との関わりがどんどん減っていって、気がついたら自分の中で深めていくだけになっていたんですよね。でも、僕は別に『資本主義社会から脱して自然と共に生きるんだ』みたいな感じで移住したわけじゃなかった。資本主義や経済とも関わりながら、探究すべきことはちゃんと探究していくってことをしたかったのに、いつの間にかバランスが崩れていたことに気がついて。探究を個人の活動で終わらせないためにも、見えてきたことはちゃんと伝えたり、他の仕事につなげたりしていく。取締役として参加するにあたって、インクワイアなら、そういうことができると思ったというのはあった気がします」
二人が共感する価値観として挙げていたのが、慶應義塾大学総合政策学部教授の伊庭崇氏が提唱する「卒・資本主義」の考え方。資本主義が可能にしてくれた恩恵や時期を否定せず認めつつも、学校を「卒業」するように、「リスペクトをもちつつ、そこから離れ、次の段階にいく」というニュアンスは、今ある社会を全く否定するわけでも、肯定するわけでもなく、探究や実践を通して新しい社会を模索していく二人のスタンスにも共鳴しています。
編集とデザインが果たす役割
山本さんは、これまでの仕事で担ってきた自分の役割を「郵便配達」にたとえます。

山本さん「僕は、“情報アーキテクチャ”という分野で長いこと仕事をしてきました。そこでは、郵便配達のように、こっちにあるデータをあっちにいる人にどう届けるかがミッションになります。複雑な情報を、グラフィックや文章などを駆使して、どうすれば受け取る人がちゃんと理解し、共感できるのかを考えるのが、間に立つ僕らの仕事です。地域に住んでいると、山や川などの自然やその土地の歴史みたいなものが単にデータとしてそこにあるだけになってしまい、上手く価値が伝えられていない状況があることに気づきます。人と自然との間に立ちながら、伝えられる形にして配達していきたい。“目の前の手紙”をどうしたら届けられるかというのは、ずっと考えていますね」
直近で山本さんが携わったのは長野県塩尻で造園業を営む「株式会社庭蒼」の新規事業立ち上げのプロジェクト。長らく造園一筋でやってきていた庭蒼が新しい事業領域に取り組むということで、会社のコンセプトを再度見直し、明文化するためのサポートを行ないました。
山本さん「今の時代にこの人たちが庭をやる意味とは何かを考え、コンセプトをつくっていきました。そのためには地域の氏神さまやお寺のことなど、土地の歴史や風習などをいろいろと調べたり、関わる人たちにもどういった幼少期を過ごしていたのかをヒアリングしたり。そうすることでようやくその人たちがここでこの仕事をやる意味みたいなものが見えてきます」

「そもそも庭とは人間にとって何なのか」というところから、一緒に考え、ブラッシュアップしながらできあがったコンセプトは、庭蒼のみなさんから「自分たちが考えてきたことはまさにこれです」と言ってもらえるものに仕上がったといいます。関わる人たちが、どういう人たちでどこからきてどこに向かっているのか。丁寧に深堀りをしていくことで時間的にも耐久性のある強度の高いものをつくるというのは、編集とデザインのプロフェッショナルであるインクワイアならではの強みの一つかもしれません。
モリさん「編集者で著述家の松岡正剛さん(※)の言葉を借りるなら、編集は『カナリゼーション(運河化)』といって時間軸を持った線として文脈や流れを整理し、相手に伴走しながら関わっていくこと。また、デザインは、その力点が『プロジェクト』をすることに置かれています。プロジェクトとはラテン語の『proicio』に由来し、前へ投げるという『pro(前へ)』と『iacio(投げる)』が組みあわさってできたものです。深く考えることがなければ、生み出すコンテンツの価値は高くなりませんし、また、どれだけ考えてもプロジェクトとしての実践がなければ机上の空論で終わってしまう。インクワイアでは、深い思想を持ちながら、しっかりアウトプットして物事を前に進めていく、編集とデザインの両輪で動いていくことを意識しています」
※松岡正剛(1944〜2024):情報や文化を独自の視点で組み合わせる「編集工学」を提唱し、日本文化を幅広く論じた編集者・著述家
養うべきは、安易に偏らず、世界を真っ直ぐに観る力
内なる好奇心から問いの探究を続けることを大事にするインクワイアが、もうひとつの経営理念として掲げるのは「変容の触媒」となること。
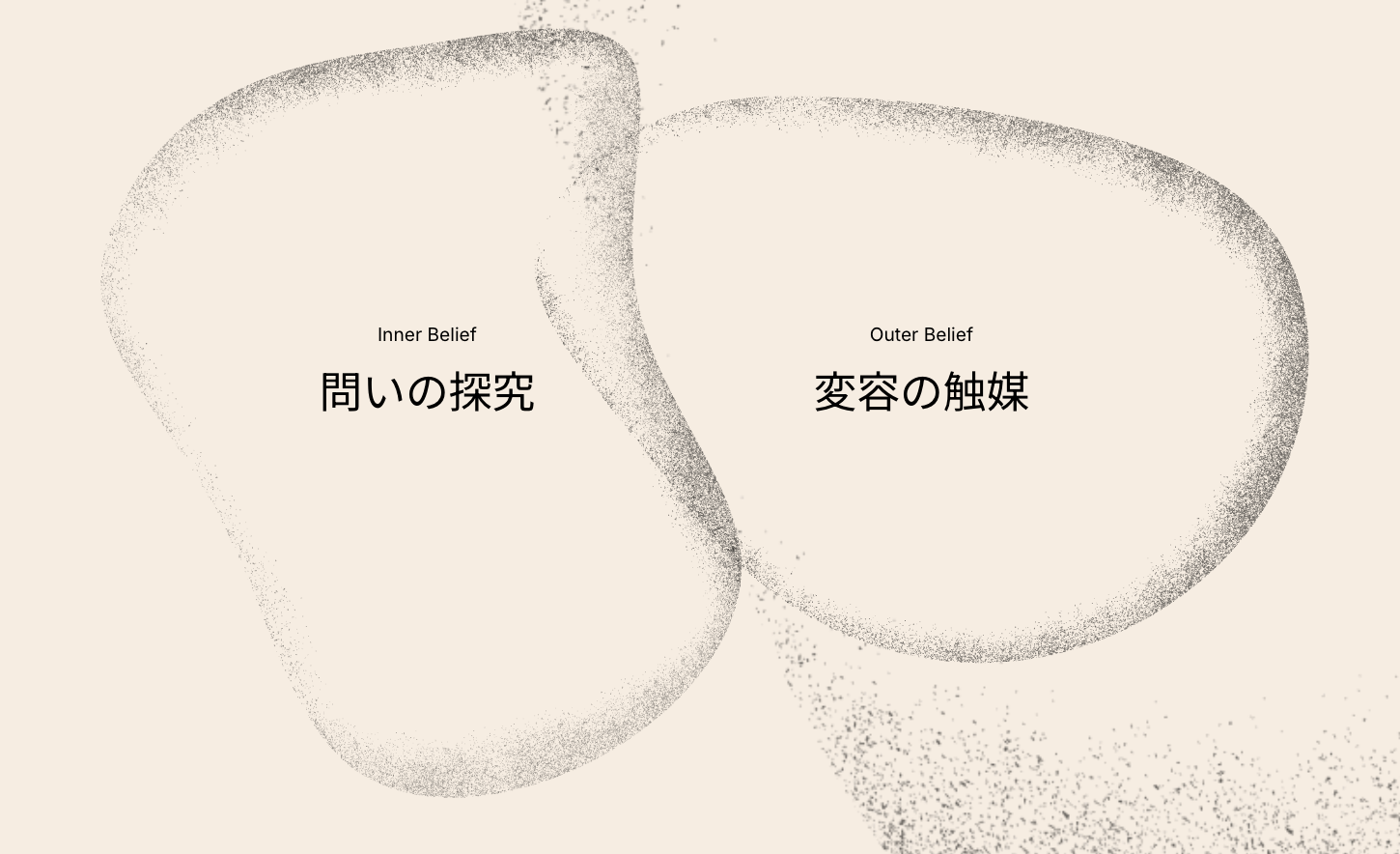
モリさん「自分たちが活動していくなかで大事だと見出すものは、実は新規のものはほとんどなくて。別の人たちが取り組んできたものだったり、別の表現をされていたりすることが多いです。一般的に“インタープリテーション(翻訳)”という言葉で表現されることが多いのですが、僕たちはいろいろなものの間に立って、世の中を俯瞰して『最近このテーマに関してはこういう語りが多いよね』と視点を加えたり、ヒアリングをした上で足りてない部分を補強したり。すでにある良いものは取り込んで、都度ベストな方向性を模索しながら“ブリコラージュ(※)”的にコンテンツをつくっていくことで、伝えたいことをちゃんと共有でき、変化を起こすことにつながると考えています」

社会に望ましい変化をもたらす触媒として求められるのは、物事の良し悪しを安易に判断せずに問い続ける力、そして今そこに立ち現れてくるものを直ちに観る直感力です。
山本さん「人間は、生きているとどうしても『何者かでありたい』と願います。そして何者かであるためには『決める』のが一番単純なんですよね。『俺は赤だなとか、いや俺は青だな』と言った方がわかりやすく、仲間も集めやすいかもしれません。でもそれがエスカレートするとポピュリズムに陥ってしまう危険性もある。世界はもっと複雑で、いろいろなものが絡み合ってできています。ラベリングして理解した気になることは簡単だけど、複雑で曖昧な世界を真っ直ぐに観ようとする方が僕らはあり方として誠実だと思っているし、それをしたいっていう人たちと一緒に仕事をしたいなと思います」

現代のような不安定な社会では、信じるものが欲しいからこそ、誰もがどこかに寄りかかりたくなります。しかし、そうして何かに偏っていった結果、分断が生まれ、争いにつながってしまうこともあるかもしれません。難しくても、大切なのは簡単に偏らないこと。
山本さん「多分大事なものは既にそこにあるんですけど、複雑に重なった瓦礫のようになっていてすぐには見つからない。それでも、そこにある複雑なものの全体をずっとみていくと、いつしか『あ、ここに宝物があるじゃん』と気付けるようになります。難しかったり、時に孤独なこともあったりしますが、本当に大事なものを見つけるためにはやっぱり簡単にどこかに偏ってはいけないと思います」
※ブリコラージュ:フランス語で「bricolage」と書き、ありあわせの道具や材料を使って、何かをつくり出すことを意味する
よりよい未来につながる無数のイノベーションの媒介者として
問いを立て、人や社会の変容につながる触媒として活動を続けてきたインクワイアチームが今回募集するのは、長野県を拠点に山本さんのアシスタントとして働く仲間。改めて、インターンを募集するに至った背景について伺いました。
山本さん「地域でやりたいことはたくさんあるけれど、それをやるための手が足りていない状況。なので、一緒に動いてくれる人を募集することでもっと多様なプロジェクトができればと思い、今回の募集につながりました」

自然の近くで活動することの意味を、山本さんは次のように語ります。
山本さん「僕らはどうしてもテクノロジーを前提に考えがちですけど、デジタル名刺にアクセスするたび、実は二酸化炭素を排出しているとか、AIサーバーの冷却に膨大な水を使っているなど、テクノロジーの先には、必ず自然環境があります。知らず知らずのうちに環境を傷つけ、消費していることに、僕らはもっと目を向けなければならない」
山本さんは、自然を探究する上でも、ウェルビーイングやマインドフルネスの観点からも、人々にとって「自然との触れ合い」や「身体性を伴った学び」が大切で不可欠だと語ります。
山本さん「ただ、都心の高層ビルの40階で『自然って大事だよね』と話しているだけでは、何も変わらないですよね。自然というのは難しくて、身体的な関わりを持たないと学べないことがたくさんあります。『この植物に触るとかぶれちゃうんだな』とか、『こうすると怪我するんだな』とか。そんな時、『そうした学びはやっぱり都会じゃなくて山の近くでやった方がいいに決まっている』というのが、すごく単純なんですけど、僕らの考えなんです」

現在は塩尻市の木曽平沢エリアでの漆製品など、自然や伝統を活かした新しい商品開発や、都市部の人と自然をつなげるリトリートプログラムの検討など、既にいくつかのプロジェクトが県内で動き始めており、インターンの方にはこれらのプロジェクトの種を一緒に考え、実行するためのアシスタントとして動いていただくことを想定しています。
今後も地域での活動はさらに展開していく予定ですが、インクワイアが求めるのは社会と向き合い、対話や議論を通じて考えを深めていくことを好む人。ただ自然や地域が好きな人というよりも、参加したプロジェクトのテーマがたまたま自然やローカルだった、という人の方が向いているかもしれません。
山本さん「インクワイアって基本的には考えることが仕事だと思うんですよね。領域は限らず、『今なんでこんなふうになっているんだろう』とか、『他にいい方法はないのかな』、『こうなったらいいんじゃないか』とか。複雑なことを楽しみながら考える人たちがもっと増えるといいなと思っているんです。古代ギリシャでソクラテスが飲んだくれながら仲間といろいろ喋る風景があったように、インクワイアに関わった人たちが考えることの大切さに気づいて、『なんかちょっと考えてみようよ』みたいなことが社会のあちこちで生まれて、楽しい時間が増えていくといいなあと」
新たな仲間を加え、インクワイアチームとして描いていく未来はどんなものになるのか。最後に、モリさんに伺いました。

モリさん「こうした多元的な世界(※)において、ローカルでの実践から見えてきたものを、僕らが媒介することで文化や地理的な差異を超えて、ローカル間での学びあいが起こっていく。特定のプロジェクトの規模を大きくするスケールアップなイノベーションというよりも、複数のプロジェクトが相互作用しながら連鎖的に発展していくスケールアウトなイノベーション創出の一端を担うことができたら、面白いんじゃないかなと思っています」
よりよい未来をつくるため、安易に寄り掛からず、社会のために悩み、考え続ける。決して簡単なことではないけれど、そのための実践はすでに起きていて、それに必要な知恵も各地で生まれています。必要なのは、目指す未来を実現するための資源を集め、必要なところに巡らせること。これから立ち上がっていくいくつもの未来を、インクワイアと一緒に、自分に問い、社会に問い、思考しながら形づくっていく人を待っています。
※多元世界(Pluriverse)とは、これまでの西洋(欧米)中心主義や、植民地主義、資本主義、科学中心主義、男性中心主義、人間中心主義といった価値観だけではなく、同じように多数存在し、つながりあっている別の世界のあり方に目を向けていく姿勢をあらわしたもの

文 岩井 美咲
編集 風音
写真 山田 智大
募集要項
[ 会社名/屋号 ]
株式会社インクワイア
[ 募集職種 ]
アシスタントディレクター
[ 取り組んでほしい業務 ]
各種プロジェクトにおける企画アシスタント及び進行管理サポート
※商品開発の企画、リトリートプログラムの企画・運営、等、内容は多岐にわたります
[ 雇用形態 ]
インターン・アルバイト
[ 報酬 ]
時給1,200円〜(昇給有り)
[ 勤務地 ]
長野県(伊那・塩尻・松本周辺)
※プロジェクトは現地での実施が基本、その他作業時はオンラインでも可
[ 勤務時間 ]
専門業務型裁量労働制
[ 休日休暇 ]
週休2日制(土・日)
祝日、GW、夏季休暇、冬季休暇(年末年始)、慶弔休暇、有給休暇、特別休暇GW、夏季休暇、年末年始、その他会社カレンダーによる
[ 昇給・賞与・待遇・福利厚生 ]
交通費支給
[ 応募要件・求める人材像 ]
・要普通自動車免許。
・人の話を丁寧に聞く、自然に向き合う、身体実感を大切にする、文化を守りたいと思う、よく本を読む、よく考える、そういった態度や習慣を大切にしている方を求めています。
[ 選考プロセス ]
書類選考
↓
面接2回(1回目:リモート、2回目:現地)
↓
採用
[ 応募締切 ]
随時募集
[ その他 ]
よろしければ、こちらもご覧ください。
