
園庭は田んぼや畑。
元気いっぱいあぜ道を走りまわる子どもたちと、のんびり草をはむヤギのグレちゃん。
「素敵な夏休みのひとコマ?」と見間違うほど、のどかな風景が広がるこの場所は、山ノ内町須賀川地区にある認可外保育施設「里山ようちえん おやまのおうち」です。園長であり、この場所を運営する一般社団法人てとての代表を務める山崎龍平(やまざき・りゅうへい)さんは、理想の保育園がつくれる場所を探して山ノ内町に移住してきた人物。

今回の求人は、山崎さんたちと一緒におやまのおうちで働く保育士の募集です。自らも遊ぶことが大好きだという山崎さんは、「もちろん経験や知識があるに越したことはないけれど、コミュニケーションを通じて一緒にこの場所の暮らしを楽しめたら嬉しい」と話します。おやまのおうちが大切にしている保育のあり方や求める人物像、地域に暮らす楽しさなどを聞きました。
保育園をきっかけに手触り感のある「地元」を守り継ぐ
取材に訪れたのは7月末。屋外で過ごす時間の多いおやまのおうちでは、この時期は水遊びや泥遊びなど、ほぼ全員が水着になって園庭を走り回ります。
山崎さん「水鉄砲の撃ち合いや、手作りのウォータースライダー、プールもあるし、田んぼではサップに乗ったりもできます。これは子どもたちからの要望というよりは、僕自身がサップに乗ってみたくて増えたもの。今日は多分、虫取りとかカエル取り、畑のお世話を一緒にしたり、草花を使って遊んだりもするんじゃないかな」
古民家を利用した園舎と、その周りに広がる園庭。かつて敷地内に建っていた蔵の敷石を利活用したファイヤーピットや木の枝にかけられたブランコ。敷地の中央には小川も流れています。

山崎さん「僕らは普通に保育園をやっているだけなんだけれど、気がついたら畑も田んぼもして、ヤギや蚕を飼って、最近は偶然園庭に住み着いた日本ミツバチの分蜂に成功して養蜂もするようになりました」
冬は雪深い北志賀エリア。小川から先の田畑があるエリアは閉鎖されますが、園舎の前は除雪機で整備をしてスキー場にあるような雪遊び場を作るなど、外遊びが多いスタンスは変わりません。
山崎さん「冬のこのエリアならでは、というところでは、バックカントリーで雪遊びもしています。ソリやカンジキを使って、子どもたちも一緒に。僕らが大切にしたいのは昔から続く北志賀高原の暮らしで、そうした暮らしの部分をみんなも一緒に楽しめたらいいよねって思っています」

現在おやまのおうちに通う園児は21名。最年長の子どもたちは、「年長さん」として責任感や体力が必要な活動をすることもありますが、基本的にクラス分けはなく、それぞれがそれぞれの興味・関心に合わせて活動をしています。開園から数年が経ち、卒園児も増えてきた一般社団法人てとてでは、保育園のほかにプレーパークや自然体験ガイド、フリースクールの運営も行っています。
山崎さん「開園当初はそこまで描いてなかったけど、どんどんつながって、広がっていって。保育園が2017年、プレイパークはコロナ禍の2020年くらいにスタートして、そのあとフリースクールを始めているんですね。なんでそういうことをしているかっていうと、やっぱり子どもたちにこの地域を見切ってほしくないから。大きな言い方をすると“郷土愛”なのかもしれないけれど、そんなに大それたものじゃなくて、この辺りで生まれた子どもたちに“地元がおもしろい”って気持ちを持って育っていってほしいんです」
周囲の自然や人との関わり、友達同士で遊んだ思い出。幼い頃に見たり、聞いたり、嗅いだり、食べたり触ったりするものたち。「そうした体験を通じて原風景が描かれていくはず」と山崎さんは言います。はじめこそ「なんでこんな子どものいないところに保育園……?」という声もあったと言いますが、仲間は徐々に増えていきました。

山崎さん「僕自身に地元と呼べる場所がないから、一生懸命になれるっていうのもあると思います。出身は山梨県だけど、もう親も引っ越してしまって家もなく、自分で自分の地元をつくらなきゃいけない。僕の子どもにとっては山ノ内町が地元だから、それをちゃんと固めてあげたいっていう気持ちがありますね。園として地域の暮らしにこだわっているのは、そういう想いもあるかもしれません」
理想の園を求めて辿り着いた里山の暮らしと循環
山崎さん自身の原風景は、幼少期を過ごした山梨県。田んぼや沼に入って遊び、川で飛び込んで泳ぎ、山に行って基地作ったり木登りをしたり、冬はスキー場に行って遊ぶこともありました。
山崎さん「基本的には山ノ内町に似ていると思います。保育の道に興味を持ったのは高校生のころ。ちょうど同時期に家庭の事情で東京に引っ越すことになったんですが、スーツを着て働く大人にはなりたくなくて、遊びが仕事になればいいなって。興味を持って調べてみたら、小さい頃の学びや遊びが大事だっていう情報に行き着いて、そこで保育専門の大学に進学を決めました」

進学先で運よく保育業界で著名な研究者の方と出会い、研究会に入って学び続けてきた山崎さん。20歳の頃には「やっぱり自分で保育園をやろう」と心に決め、社会人になってからも対談を企画したり、勉強会を開いたり「理想の保育園ってなんだろう」を追求し続けました。
山崎さん「その過程で基本的な専門知識が身につきましたし、人のつながりも全国にたくさんできました。最初に就職をしたのが、宮崎駿監督が作ったジブリの保育園だったので、そこでの学びも印象的でしたね。宮崎さん曰く“人は大人になるまでの間に、必ず宝箱を全部ひっくり返すときが来るから、それまでに好きなものをたくさん詰め込んであげなきゃいけない”って。確かにそうだなって思って」
子どもたちが将来のことを考えるとき、自分のなかに暮らし方や生き方の選択肢がたくさんある方が、より豊かな大人になっていけるのかもしれない。以来、「子どもたちの宝箱の中身を増やす」ことは、山崎さんが大切にする考えのひとつになっています。

山崎さん「東日本大震災をきっかけに子どもたちの遊ぶ環境がどんどん厳しくなっていくのを目の当たりにして、いよいよ理想の場所を探そう、と移住を決めました。まずは就職をして働きながら開園を目指す予定だったので、せっかくなら一生やることのなさそうな仕事をしようと思って。一次産業か二次産業で職を探して、見つけたのが山ノ内町の須賀川地区にある牧場だったんです」
「やっぱり牧場ってすげえんだなって、思った」と笑う山崎さん。働き始めて、改めて牧場も含めた地域全体が循環していることを意識するようになりました。
山崎さん「例えば、菓子用に加工されたりんごの皮やりんごジュースの絞りカス、大豆を加工したあとに出るおからが牛の餌になる。牧場には、あちこちの産業で廃棄されるものが集まってくるんです。使い終わったきのこの培養土が牛の寝床に敷かれていて、それらが牛の排泄物と混ざって堆肥になる。そうすると今度はその堆肥を取りに農家さんがやってきて、代わりに藁を持ってきてくれて。そうやっていろんな循環を目にするようになりました」
動物の世話以外にも、重機や車の操縦やメンテナンス、雪かきの仕方、水道工事など、この地域で暮らすための知恵は牧場で教わり身につけてきたスキルです。同時に園の場所探しも進め、つながりのなかで紹介されたのが今の場所でした。

山崎さん「最初に見たときはもっと岩も木もたくさんあったし、庭には納屋や蔵など、建物がいくつか建っていました。それでも“この場所だ”って直感をして、バックホーを借りて自分で整備したり、砂場も作って小屋も建てたり。牧場で見聞きした循環を、ここでもだいぶ取り入れています」
山崎さんが理想としていた「日々の行いがまわりまわって自分に還ってくるような暮らしの在り方」は、元を辿れば北志賀のような「里山」で古くから育まれてきた考え方です。日本独自の言葉だといわれる「里山の暮らし」をもう一度見直したい。「里山ようちえん おやまのおうち」という名前には、そうした山崎さんの願いが込められています。
自然もひとつのツールと捉え、子どもの身体と心を育む
外で過ごす時間が多いおやまのおうちですが、「あくまで普通の保育園」というスタンスもこだわりのひとつです。

山崎さん「田んぼがあって畑があって、小川が流れていて。ここを走り回っているだけで、自然と足腰が強くなって丈夫な身体が育っていくんです。身体をしっかり育ててあげると、ちょっと転んだくらいでは折れない心も育つ。せっかく身の回りにたくさんの自然があるから、そうやって子どもたちが自立していく環境を整えたいとは思っています」

山崎さん「一方で長野県には、そうした自然を生かした保育を行う園に向けて“信州型自然保育認定制度※”が作られていますが、うちは特化型の認定ではなくあえて普及型の認定をとっています。子どもを育てるのは人であって、自然をどう使うかも人次第。屋内より屋外がいいとか、テレビやアニメより土いじりがいいとか、添加物の入ったおやつより畑の野菜がいいとか、自然が万能だということを謳いたいわけではないんです」
お菓子も食べるし、スマートフォンやパソコンで配信を見ながら踊りの練習もする。身の回りにあるものを「排除」や「否定」するのではなく、一旦受け入れて付き合い方を考えていく。生活を便利にする機器や食材、身の回りにある自然も「どれも上手に付き合うことで子どもの心や身体がよく育つ」と山崎さんは考えます。

山崎さん「僕ら大人が排他的な考え方をしていると、それはどうしても子どもたちに伝わって、最終的には人を排除しようという思考につながっていくと思っていて。おやまのおうちは、基本的に全てを受け入れる。受け入れた上でどうやって付き合うかを学び、考えたいですね。1番大事にしているのはやっぱり“暮らすこと”。そのなかで遊び、トラブルが起きれば話し合いをして、保育にあたっています」
生きていく上では、理不尽に感じることも不自由に感じることもたくさんある。それでも工夫して楽しいことを見つけられるよう、おやまのおうちでは、みんなで暮らしを作っていく楽しさを子どもたちに伝え続けています。
※信州型自然保育認定制度:長野県が認定する保育制度。豊かな自然環境や地域資源を積極的に活用し、屋外の体験活動を多く行う保育のことを指す。2015年に始まり、2025年8月時点の認定園数は313園
保育の専門性と好奇心を軸に地域と向き合う暮らしを
改めて今回の求人は、山崎さんたちと一緒に「里山ようちえん おやまのおうち」で働く保育士の募集です。今は保育士資格を持つ山崎さんと薫さん、他に3名のスタッフがシフト制で保育をしています。
自身も子育てをしながら週に4日だけ勤務をしている町外の保育士さん、山ノ内町に住んでいて週に1日見守りに来るおばあちゃん、4人の子どもを育てた経験を活かして見守りに入っている方など、資格や経験の有無はさまざま。

おやまのおうちでは、通常保育のほかにお泊まり保育や秋祭りなどさまざまなイベントもあり、地域の人との関わりがあるのも特徴です。
山崎さん「募集しているのは専門資格を持った保育士ですが、いわゆる“保育園の先生”というよりも、地域の子どもたちと一緒に暮らしていく大人であり、コミュニティの一員だと考えてもらうといいかもしれません。フリースクールに来ている小学生と一緒に活動をすることもありますし、とにかく多様で、広いコミュニティに接続しています」
おやまのおうちの卒園児は自動的にフリースクールに登録される仕組みになっているので、小学生になってもそのまま園に出入りができます。さらに長期休みには、小学4年生以降を対象に保育のお手伝いをしてみたい子を募り、小さく職場体験をすることも。
山崎さん「子どもたちのスタートアップを支援している感覚ですね。月に1度は小学生の日を作っていて、卒園児たちがやってきます。ただただ遊ぶだけの子もいれば、みんなのお昼ご飯を作ってくれたり、土木部として草刈りや小川の護岸工事をやってくれる子もいたり。みんなの役に立つことで、誇らしさも感じてくれたらいいなって思っています」

山崎さん「うちの祭はステージ発表をしたり掲示物を発表したり、いろんな企画があるんだけれど、小学生になるとお店の出店もできるんです。この日だけ使える通貨があって、ステージ発表をすると出演料がもらえたりする。お店を出店して出した売り上げは、後で換金する仕組みもあって、これもやっぱり遊びながら学ぶための場になっているんです」
小学生の出店は、クレープ屋さんにかき氷屋さん、ゲーム屋さんや工作コーナーなど様々。出展を希望する子どもたちは、事前に出店説明会に参加して事業計画書を作り、出店後には決算報告書も作成するといいます。
山崎さん「例えば材料に畑のきゅうりを使ったら仕入れの原価が抑えられるとか、どんなコンテンツを用意したらより多くの人に楽しんでもらって、報酬を得られるかとか。夢中になって考えて、楽しんでいるうちに日々の暮らしや社会を見る目も養われていく気がします。もちろん子どもだけじゃなくて大人も本気で出店をするので、誰のお店がウケるのかは当日までわからない。ほんの少しでも社会や経済に触れてもらって、算数とか国語とか、学校の勉強の楽しさや必要性を感じてほしい狙いもあります」

取材の翌日は、月に1度、保護者と一緒に行う整備作業の日。道具を使える人は畑仕事をしたり草刈りをしたり、道具のない人たちは野外調理でみんなのお昼ご飯を作ったりします。「午後には遊びが始まって、だんだん整備をしているのか遊んでいるのかわからなくなります」と笑う山崎さん。
みんなで手を加えたり使ったりするからこそ、自然と場や地域に愛着が湧いていく。「どうしたらこの先の地域により良い未来を描けるのか」、そんな問いを共に持てる人も、働き手として向いているのかもしれません。
移住者も多い北志賀エリアは「なにかやりたい」思いにもぴったり
暮らしに根差した保育を行うおやまのおうちですが、応募時点では山ノ内町の知識や田舎暮らしの経験はなくても大丈夫。就職をきっかけに移住をする方も受け入れ、ここで働きながら、知識や文化を身につけていく想定をしています。

移住者がじわじわ増えているという山ノ内町では、保育園がある北志賀エリアだけでも、コーヒー焙煎をする人やパンを焼く人、焼き菓子屋さんにピザ屋さん、キャンプ場をつくるなど、さまざまな取り組みが広がっています。
山崎さん「近くは、長野市からの移住とかも聞きますね。多分このあたりには少し隠れ家みたいな雰囲気があって、“なにかおもしろいことができそう”っていう余白があるんじゃないかな。ここ数年の新しい流れのなかで、観光や農業、ウィンタースポーツや温泉、これまでつながっていなかった地域の活動がゆるやかに一緒に動き始めた感覚もあって。保育園以外のそういった地域の出来事にも顔を出してみると、どんどん世界が広がっていくと思います」

山崎さん「就職をきっかけに県外や町外から移住をしてくるのであれば、宝探しに来るような感覚で“おもしろいものないかな”って、自分の好奇心みたいなものに従っていける人がいい。あとはやっぱり、子どもたちと一緒に泥だらけになって遊ぶとか、一緒にヤギや蚕、畑や田んぼの世話をするとか、冬には雪かきをするとか、そういうところですね」
最終的には、地域がもっとおもしろくなって、この場所で育った子どもたちが、大人になっても働いたり、暮らしたり、遊んだりできる状況をつくりたい。「こうやって田んぼで遊んでいる子どもたちが、もしかしたら地球規模の問題を解決しちゃうかもしれないんです」と笑う山崎さん。小さな山間の保育園から、暮らしの知恵と文化を楽しみ、守る仲間を探しています。
文 間藤まりの
編集 風音
撮影 関亮太
募集要項
[ 会社名/屋号 ]
一般社団法人てとて 里山ようちえん おやまのおうち
[ 募集職種 ]
正規保育士
[ 取り組んでほしい業務 ]
保育業務全般
[ 雇用形態 ]
正社員
[ 報酬 ]
165,300円(10月以降改定予定 177,000円)
[ 勤務地 ]
〒381-0405 長野県下高井郡山ノ内町大字夜間瀬8887番地
[ 勤務時間 ]
8:30〜17:30(内1時間休憩)
[ 休日休暇 ]
・週休二日制(土日)、祝日
・その他
園行事により土日祝の勤務日あり
夏休み、年末年始休み、春休みあり
・6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日
[ 昇給・賞与・待遇・福利厚生 ]
・昇給年1回
・通勤手当5000円/月
・社会保険加入(健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金)
[ 応募要件・求める人材像 ]
保育士資格必須
自然体で子どもと触れ合うことができる方
里山の暮らしや遊びを楽しめる方
探究心のある方
経験値は問いません。保育の方法については丁寧に指導します。
[ 選考プロセス ]
面接(履歴書持参、現地)
[ 応募締切 ]
2025年12月31日(内定者決まり次第打ち切り)
[ その他 ]
よろしければ、こちらもご覧ください。
個別相談も可能です
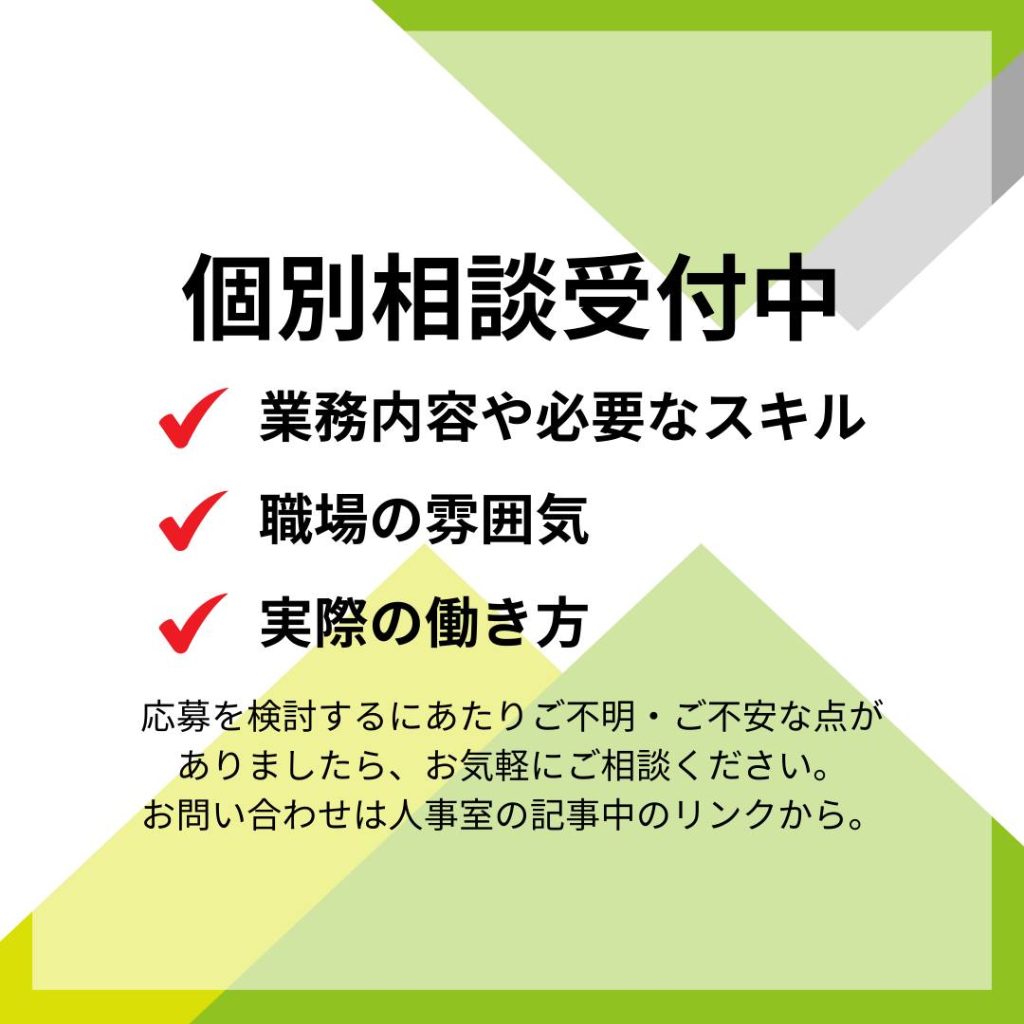
応募前に質問や確認したいことがある方は個別相談を受け付けます。
◎企業担当者と応募前に事前に説明や相談を行うことができます。
どんな会社なのか、実際の働き方はどうなるかなど、気になる点をざっくばらんにお話ししましょう。
